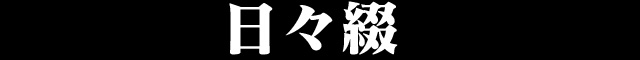はじめに:2.0は本当に新時代なのか?
World of Tanksが迎えたアップデート2.0。
Tier XI車輌の導入、格納庫およびユーザーインターフェースの全面リニューアル、数百輌規模の車輌バランス調整、再設計されたマッチングシステムの導入と、まさに「史上最大」の名にふさわしい大規模アップデートだ。
北米βから参戦し、アジアサーバー移行後も10年以上の付き合いがあるものの、正直に言えば最近は年に1回程度しか起動しないような「休眠プレイヤー」状態だった筆者。
それが8月の15周年イベント目当てでログインしたところ、突然の2.0発表に遭遇。
結果として8月から1ヶ月以上も連続でプレイを続けている状況だ。
※2.0の詳細なレビューについては、先日の記事で詳しく紹介しているので、そちらも併せてご覧いただきたい。
果たして2.0には、長期間離れていたプレイヤーを再び戦場に引き戻すだけの魅力があるのか?
実際にプレイした感想をもとに、2.0の魅力と課題を率直にレポートしたい。
TierXIの衝撃―新しい頂点との出会い
TierXのIS-7とBadgerでの日常戦闘
2.0以降、筆者は主にTierX車輌のIS-7とBadgerを使用している。
どちらも1勝するまでプレイするというマイスタイルを続けているが、戦場の雰囲気は確実に変わった。
最も印象的なのは、16輌の新たなTierXI車輌との初遭遇だ。
これまでTierXが最高峰だった戦場に、さらに強力な存在が現れたのだ。
実際に対峙してみると、「やっぱり強いなぁ」という部分もあれば、「乗り手によってはすごく弱いなぁ」という場面も見られる。
車輌性能の向上は間違いないが、結局のところプレイヤーのスキルが勝敗を左右する基本は変わらないようだ。
「全然貫通しねぇじゃん」という場面もあれば、「意外と抜けるな」という発見もある。
これは新しいTierXI車輌の装甲配置や弱点を理解していく過程の楽しみでもある。
徐々に増えるTierXI―戦場の力関係に変化
アップデート直後と比べて、TierXI車輌の数は徐々に増加している。
これによって、従来のTierX戦場の力関係にも微妙な変化が生じている。
まだ「様子見」という段階だが、今後数ヶ月でこの新しいバランスがどう定着していくかが注目ポイントだ。
マッチングシステム:改善されたのか、それとも…?
「マッチング賢くなった」は本当か?
新システムでは、車輌のタイプだけでなく、それぞれの車輌のプレイスタイルも考慮されるようになりますとのことだったが、実際の戦場での体感はどうだろうか?
正直に言えば、「マッチング賢くなったというのは嘘過ぎるなぁ」というのが率直な感想だ。
相変わらず大味な試合ばかりで、「何もしないでも勝っちゃう試合」や「何もできないまま蹂躙されて1-15で負ける」といった極端な展開が続いている。
むしろ「以前のマッチングよりひどくないか?」と感じる場面すらある。
公正なマッチングが実現されてこそ、プレイヤーのスキルやチームの戦術が意味を持ち、両チームに等しく勝つチャンスがあるという理想とは程遠い状況だ。
マッチング待機時間の波
興味深いのは、マッチング待機時間の変動だ。
ある日は「3分経ってもマッチング終わらない」という状況が頻発したかと思えば、翌日は「すんなり決まる」ようになる。
これはサーバーの調子やプレイヤー人口の変動によるものかもしれないが、安定性という点では課題が残る。
自走砲(SPG)問題の変化
プレイしていて気づいたのは、SPG(自走砲)の数が減った印象があることだ。
「SPGにポンポン打たれて死ぬ」という場面が以前より少なくなっている。
これはマッチング・システムにより、可能な場合は1つのチームに属する自走砲の数は0~2輌になるように調整されますという調整の効果かもしれない。
SPGが少ないことで、より積極的な戦術が取りやすくなったのは確実にプラス要素と言える。
大規模バランス調整の影響
『World of Tanks』史上最大のバランス調整と謳われる今回のアップデートだが、実際のプレイ感覚への影響はどうだろうか?
TierVII車輌の育成も継続しているが、確かに初期状態の車輌がより戦いやすくなった印象がある。
モジュールの改良と不要な要素の削除により、初期状態の車輌がより強力になりましたという変更は、特に中低Tier帯で顕著に感じられる。
ゲームの本質的な魅力―変わらぬ面白さ
ストレスと楽しさの共存
World of Tanksをプレイしていると、「やり出すと面白い」のだが「ストレスは溜まる」という二面性は相変わらずだ。
大敗と大勝が極端に分かれがちで、「独りでどうにかなるような物でもない」チーム戦の宿命的な課題は2.0でも解決されていない。
しかし、だからこそこのゲームは面白い。
個人のスキルとチーム戦術、運と判断力、そして車輌知識が複雑に絡み合って生まれる戦場の緊張感は、他のゲームでは味わえない独特のものだ。
長期プレイヤーの視点―1年ぶりの本格復帰
北米β時代から数えると10年を超える付き合いになるが、ここ数年は年に1回程度しか起動しない「休眠状態」だった。
それが2.0をきっかけに8月から1ヶ月以上連続でプレイしているというのは、自分でも驚きだ。
何がこれほどまでに引きつけたのか?
新しいTierXI車輌への興味、インターフェースの改善、そして久しぶりの戦車戦への郷愁―複数の要因が重なって「やっぱり楽しい」と感じられるのがこのゲームの魅力だ。
ブランクがあったからこそ、2.0の変化がより鮮明に感じられる面もある。
以前の記憶と比較して、「ここが良くなった」「これはまだ課題だ」という判断ができるのは、むしろ客観的な評価につながるかもしれない。
今後の展望―2.0時代の戦場
アップデート2.0は確実にWorld of Tanksに新しい風を吹き込んだ。
TierXI車輌の存在感、インターフェースの改善、バランス調整の効果など、ポジティブな変化は間違いなく存在する。
一方で、マッチングシステムの改善については、まだ発展途上という印象が強い。
理想と現実のギャップは大きく、プレイヤーの期待に応える水準に達するまでには時間がかかりそうだ。
それでも「あと1ヶ月はプレイするゲームの中心となりそう」と感じるのは、やはりこのゲームの根本的な魅力が健在だからだろう。
新しい要素に適応しながら、戦車戦の奥深さを味わい続けていきたい。
まとめ:2.0は休眠プレイヤーを呼び戻す力があるか?
World of Tanks 2.0は、間違いなく大きな進歩だ。
そして何より、15周年イベント目当てで久しぶりにログインした筆者が、2.0の発表と実装を経て1ヶ月以上もプレイを継続しているという事実が、その魅力を物語っている。
当初は単発的なイベント参加のつもりだったが、2.0の圧倒的なスケールと新鮮さに引き込まれ、気がつけば毎日のように戦場に向かっている。
TierXI車輌という新しい頂点、改良されたインターフェース、大規模なバランス調整―これらの要素は確実にゲーム体験を向上させている。
マッチングシステムのような課題は残るものの、ゲームの本質的な魅力は健在だ。
むしろブランクがあったからこそ、改めてWorld of Tanksの面白さを再発見できた面もある。
2.0時代のWorld of Tanks―偶然のログインから始まった復帰だったが、結果として「休眠プレイヤー」にとって復帰する絶好のタイミングであることが証明された。
少なくとも筆者にとっては、「あと1ヶ月はプレイするゲームの中心」として十分な魅力を持った進化を遂げている。