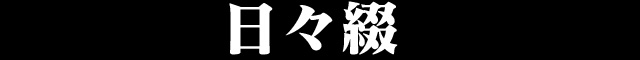Cities: Skylines II(シティーズスカイライン2)の情報
Cities: Skylines 2の公式情報「Economy 2.0 Dev Diary #1」をさらっと翻訳して読み解いていきたいと思います。
Client Challenge
Economy 2.0 Dev Diary #1
Economy 2.0 開発日誌 #1
こんにちは!また開発者日記をお届けします。
今回は今後2週間以内にリリース予定の経済再構築、いわゆる「エコノミー2.0」について見ていきます。
皆さまから数多くの貴重なフィードバックをいただきました。
バグを報告したり、ゲームをプレイした際の感想を共有してくれました。
これらのフィードバックを検討する中で、特に経済シミュレーションが透明性に欠けており、都市の管理に十分なコントロールができないことが明らかになりました。
この点を改善することが重要だと感じ過去数か月間にわたり、皆さんのフィードバックに基づいていくつかのシステムを全面的に見直しました。
詳細に入る前に、皆さまから寄せられた貴重で建設的なフィードバックに感謝したいと思います。
皆さまのフィードバックのおかげでどのような問題が発生しているか、どんな情報が不足していたのか、そして改善の糸口を見つけることができました。
今回の変更後のフィードバックも楽しみにしています。
皆さまの声を参考にし、Cities: Skylines IIをさらに良いものに育てていきたいと考えています。
それでは、エコノミー2.0の内容に入りましょう。
エコノミー2.0の目標は、システムをよりストレートに分かりやすく、対応力の高いものにすることでした。
そうすれば、皆さまにより意味のある選択をしていただけるようになり、さまざまな側面をより制御できるようになります。
つまり表面的には見えない自動化されたシステムやセーフガードは少なくなり、挑戦が増えるということです。
初心者でも成功できる程度のゲームプレイは維持しつつ、熟練者には最適化による恩恵が得られるようにしたいと考えています。
詳細は後ほど説明しますが、エコノミー2.0の主な変更点は以下の通りです。
- 政府補助金が削除され、経済がより挑戦的で透明になります。
- 外部接続からの都市サービスの輸入にトグルと料金が追加されました。
- 都市サービスの維持費が増加しました。
- 需要の計算が改善されました。
- 新しい家賃と家計支出の計算式で低密度住宅への居住が可能に
- 生産チェーンの再調整によって税収が適正な水準に
経済
皆さまからのフィードバックで最も多かったのが、このゲームでは市の財政管理がさほど難しくないということでした。
適切なバランスを見つけるのが難しいのは事実です。新規プレイヤーにも簡単に始められるようにしつつ、Cities: Skylinesの熟練プレイヤーやシティビルダーの長年のファンにも挑戦を提供したいと考えています
Cities: Skylines IIでは、都市が確立される際の助けとなるように政府補助金を導入し、経費に応じてスケールするようにしました。
しかしこれによりゲームから主体性と結果が取り除かれてしまいました。
政府がユートピアのすべての経費をカバーするなら、なぜバランスの取れた経済を持つ都市を作る必要があるのでしょうか?
政府補助金については様々なアプローチを検討しましたが、最終的には都市予算から完全に削除することに決定しました。
これにより都市の財政を完全にコントロールし、支出のタイミングと内容を考える理由が生まれます。
利益を上げる都市を作るのはあなた次第であり、成功した時にはすべての功績を手にすることができます。
もし慣れるのに苦労する場合は、ゲーム内のチュートリアルや、右上の質問マークでアクセスできるアドバイザーのヒントが役立ちます。
また私たちや他のプレイヤーに助けを求めることもできます。
お金
お金は世界、つまりこの場合は都市を動かします。
Cities: Skylines IIでは、お金は都市内で循環し、シミュレーション内外でお金の源と流出によって循環します。
Cities: Skylines IIでは、以下の4つのエンティティを扱います。
- プレイヤー/都市
- 世帯
- 企業
- 投資家(抽象化)
それぞれが収入源と支出源を持っています。
一部は設定済みで自動的に動作しますが、コントロールできるものも存在します。
以下で概要をお伝えしますので、皆さまの街でどのようにマネーが流れ、どう影響できるのかご理解いただけると思います。
(画像省略)
都市サービス
市民サービスの建設や維持費、そして道路費用が、ほぼ全ての支出先となります。
コノミー2.0では市民サービスコストを再調整しており、維持費が大幅に増額されています。
これにより、街が成長するごとに選択の意味合いが重くなるはずです。
市の経済は大学を賄えるだけの力があるのか?
それとも税金を上げる必要があるのか?
郵便サービスを改善して市民の満足度を上げるのか、それとも経済が安定するまで待つべきか?
このような問題に直面することになるでしょう。
ただしサービスは地元だけでなく、隣接都市の外部接続からも提供できます。
例えばゴミ収集車や救急車などです。
当初は(電力、上下水道を除き)輸入サービスの唯一のコストは、サービス車両が到着し作業を行うまでの時間でした。
エコノミー2.0ではこれに人口に応じた手数料が加わります。
しかし手数料を払いたくない場合もあるはずです。
そこで新しい市政策「市民サービス輸入」を追加しています。
有効/無効のトグル式で、有効時は不足しているサービスを輸入できますが、無効時(デフォルト)は地元のサービスのみが利用できます。
現時点ではオール無しの選択しかできませんが、より細かい制御が可能になるよう検討中です。
皆さまの意見をお聞かせください。
どのような方向性が望ましいでしょう
都市生活
この「エコノミー2.0」という呼び名からも分かる通り、経済シミュレーション以外にも影響があります。
1.1.0f1で導入された地価システム改善に加え、需要、家賃、教育、市民の幸福度にも手が加えられています。
これらの変更は、市民の生活や彼らが住む場所の選び方に影響します。
需要
最も顕著な変更は、需要算出方法の見直しです。
より反応が良く都市の状況を正確に反映するようになりました。
住宅需要では、密度の希望値が世帯の規模と富裕度に応じて変わります。
一般的に低密度住宅が最も高価格帯で、一世帯が建物の費用(家賃と維持費)を全額負担します。
中高密度居住では費用が分散されるため安価です
裕福な世帯が増えれば低密度需要が高まり、学生などの低所得者が増えれば高密度需要が高まります。
同様に、家族は広い低中密度住宅を、単身者は高密度の狭い住宅を望む傾向にあります。
新たに誕生する世帯の種類は、平均市民幸福度、ホームレス人口、住宅税率、教育機関の空き状況、雇用状況によって決まります。
商業需要に目を向けると、世帯のニーズとより密接に関係するようになりました。
世帯の消費が増えれば商業地区への需要も高まります。
買い物に行く前に、家賃とゴミ手数料を払わねばならないようにし、世帯の購買ニーズを調整しました。
さらに、商業施設に入居可能な企業の種類を、市民が消費する製品とより密接に関連付けました。
つまり同種の企業が次々と立地するようなことはなくなり、より多様な製品が提供されるようになります。
オフィスと工業の需要は、他の用途地域に見合うよう適正化されました。
商業地区との連携も強化され、必要な製品を地元で生産できるようになっています。
さらに工業地区には働く場所が増え、需要をより簡単に満たせるようになっています。
教育と仕事
以前から教育システムには手を加えており、特に十代の生徒を高校に通わせることを目指してきました。
しかし目標を完全に達成できたわけではありません。
そこでエコノミー2.0では教育システムをさらに改善しています。
子どもは市に空きがあれば必ず小学校に通います。
十代の生徒も高校に通う確率が高くなりましたが、職を選ぶ者もいます。
特に高校がない場合です。
小中学校の卒業率も向上しています。
また高校を卒業していない成人も、空きがあれば低確率ながら高校に通えるチャンスがあります。
十代と大人はともに、適切な仕事があれば就労できます。
ただし、病気やケガなどで健康状態が優れない場合は、就労可能な市民とはみなされません。
治療を受けた後でなければ働けません。
市内で空きがあれば就労できますが、なければ隣の街で働くことになります。
隣の街で働くのはあまり好ましくはありません。
仕事が見つからなければ失業者となり、政府から失業手当を受け取ります。
しかしこの選択肢は一時的なものです。
適切な雇用機会を与えられなければ、いずれは家賃が払えずに市外に転出するしかなくなります。
ビジネスの構築
市は市民だけでなく、様々な企業の拠点でもあります。
そして需要だけでなく商業、工業、オフィスにも変更がありました。
生産から見ていきましょう
。皆さんも基本は理解していると思います。
1つ以上の原材料が投入され、より付加価値の高い製品に加工されます。
これには労働者と時間を要します。
高学歴の労働者の方が効率的で、製品ごとに設定された一定量の作業工数が必要です。
以前は作業工数はゲーム開始時に計算していましたが、それを事前設定の値に変更し、予測可能性を高めたうえで細かい調整を加えやすくしました。
さらに全製品の作業工数を減らしたため、全体的な生産量が抑えられ、企業の利益、ひいては徴収できる税収も減りました。
さらに資源価格の算出方法と価格そのものにも手を加えています。現在は2種類あります。
産業企業が原材料を購入する際の割引価格と、商業企業が製品を仕入れる通常価格です。
両者を組み合わせた価格で最終消費者に販売されます。
こうすれば誰もが(少なくともある程度は)利益を得られるはずです。
でも心配無用、賃金水準を上げてあるので、市民は住居と必需品を賄える収入があります。
たくさんの情報を伝えてしまいました!
ここで本日の開発者日記を終えますが、次回は家賃、建物のアップグレード、既存の都市への影響について取り上げます。
かなり開発日誌となっていました。
もう少しで経済に修正を入れたアップデートが来るようです。
その中身を説明してくれています。
さらっと読んでましたがけど…若干難しいですね。
分かったのは補助金が無くなってしまったり街の経営はかなり難しくなると言う部分ですかね。
今のままではぼろ儲けしすぎになってしまうのでそこへの対応という感じが大きいのでしょうか。
そこはあまり拘っていなかったのですけども、都市ゲームとしてはぬるげーになっていたので改善するんでしょうね。
それよりも早くアセット出してくれーって感じですけど。
ジオラマ勢はその辺が重要ですから!!!
※画像はクリックでオリジナルサイズ
※このページでは、Paradox,Colossal Orderが権利を所有する画像を利用(引用)しております。当該画像の転載・配布は禁止いたします。